誰もが憧れる、フェデラー選手のような片手バックハンドストローク。
ただ、両手バックハンドに比べて難易度が高いと思われていることが多いです。
「力が入らない」「安定しない」「コントロールできない」などお悩みは多岐にわたります。
片手バックハンドストロークを安定させるコツをhachizooと一緒に学んでいきましょう!
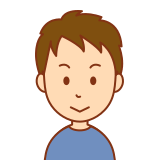
ソフトテニス経験者で硬式テニスを始めたため、片手バックハンドを選択しました。
ですが、いまいち打点や身体の使い方が出来ません。
力が入らなかったり、コントロールできなかったり、悩みは尽きません。
どうすれば安定させることが出来ますか?
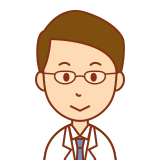
フォアハンドの逆の動きが中心となる両手バックハンドストロークとは違い、
片手バックハンドストロークの打点や身体の使い方は特殊ですよね。
難易度が高く、挫折してしまう方も多いですが、覚えればメリットも多く何より格好良い!
片手バックハンドストロークが安定するコツを一緒におぼえていきましょう!
この記事で分かること
片手バックハンドストロークが安定しない原因と解決法
・打点に間に合わないため、差し込まれて力が入らなくなってしまう
→打点から逆算してテイクバックとスタンスを間に合わせるようにしよう!
・身体が正面向きまで開いてしまい、ボールを引っ張って飛ばしてしまう
→ラジオ体操を参考にしながら、前の肩が開かないフィニッシュを身に着けよう!
・非利き手を離すのが早いと、手打ちになってしまう
→テイクバックは非利き手で!肩の入りを意識しよう!
※この記事は右利きの方という想定で記載します。左利きの方は逆で考えてください。
片手バックハンドストロークが安定しない原因と解決法
打点に間に合わないため、差し込まれて力が入らなくなってしまう
片手バックハンドストロークの標準グリップである「バックハンドイースタングリップ」は包丁持ちのコンチネンタルグリップよりもややバックハンド側に(左側)にずらして握ります。バックハンド側に少し厚くなるグリップとなります。
また、片手バックハンドストロークは前の肩(右肩)が支点となりスイングするショットですので、力を入れて打球するためには打点が相当前になります。このことを考慮しないと打点に間に合わないことが増えてきてしまいます。
初級者の多くの方がフォアハンドストロークの打点を基準に考えてしまいがちです。しかし、フォアハンドストロークは後ろの肩(右肩)が支点になりますので、やや厚めのセミウエスタングリップでも打点は片手バックハンドよりも後方になります。
フォアハンドと同じような準備で入ってしまうと、相当の確率で振り遅れてしまうという事です。
また、スタンスにも注意が必要です。フォアハンドストロークはオープンスタンスが主でも全く問題ないのですが、片手バックハンドは右肩主導ですので右足を前に踏み込んで打球することが主です。前に踏み込んで打球する分、時間が無くなりますので、振り遅れてしまう確率が上がってしまうわけです。
これらの原因の結果、「打点に間に合わない」という事が、片手バックハンドストロークで挫折してしまう方の多くの理由となっています。
解決法→打点から逆算してテイクバックとスタンスを決めるようにしよう!
打点に振り遅れないために、そこから逆算して考える方法があります。力の入る打点を把握したら、そこに至るまでの準備動作(テイクバックやスタンスなど)を間に合うように逆算して考えます。
具体的には、「テイクバックは自コートにバウンドする前に始動出来ると間に合うな。」というような感じです。相手のボールのスピードにもよるのですが、どれだけ準備動作を早く始動出来るかを是非考えてみてください。
特に、「スタンスの決め方」には工夫をしましょう。単純に右足を前に踏み込んでしまえば、バウンド地点に近づいて突っ込んでいくことになり時間が足りなくなります。
レディポジションからの第一歩目は、左足を斜め後ろに動かす(下がる)ことをお勧めします。こうすることで、まずは飛んでくるボールとの距離を取れます。それから右足を前に踏み込む。そうすれば振り遅れる可能性はグンと減ってくるはずです。
「飛んでくるボールと間合いを取るために、いったん下がる」スタンスはこのような工夫を是非してみてください!
身体が正面向きまで開いてしまい、ボールを引っ張って飛ばしてしまう
打球がまっすぐに飛ばずに悩んでいる方は、右肩が打球時に回り過ぎてしまっていることが多いです。こうなると身体は正面向きになり、右肩は右方向に向いてしまいます。ボールも右方向に引っ張って飛ぶことがほとんどになってしまいます。
フォアハンドストロークや両手バックハンドストロークは身体が正面を向いて終わることが多いので、片手バックハンドストロークも同じになってしまうという事です。片手バックハンドストロークの右肩を若干閉じて身体が開かないようにする動作は特殊ですので、慣れないと難しいです。
また、右手で打つ片手バックハンドストロークですが、かといって左手を全く使わないと、すべての力が右手に引っ張られてしまいます。結果、右手に身体が振り回されてしまうことになり、これまた身体が開いてしまう原因になってしまいます。
解決法→ラジオ体操の動きで右肩が開かないようにフィニッシュしよう!
片手バックハンドストロークをまっすぐ飛ばすためには、右肩がテイクバック時は斜め後ろ向き、フィニッシュ時は斜め前向きになっていることが必要です。それよりも右肩が回り過ぎてしまうと引っ張った打ち方になってしまいます。
また、まっすぐ方向にパワーを伝える方法として、肩甲骨(肩の後ろの筋肉周り)を閉じていく動きが出来ると効果的です。
右肩が開かないことと、肩甲骨を閉じる動き、この2つを習得するうえで効果的なのが、「ラジオ体操第一で二番目に行う動作」です。「腕を振って足を曲げ伸ばす運動」と名前がついています。
クロスした右腕と左腕を、胸を張りながら横に伸ばす動き。この時肩甲骨が閉じることを感じられるかと思います。ポイントは「右腕だけでなく左腕も使う事」が大切です。
片手バックハンドストロークに戻ると、右腕は前へ振り出しますが、同時に左腕は後ろに振り出す。そうするとフィニッシュの時に左腕が後ろにいく分、右肩は斜め前向き以上開かなくなります。また、肩甲骨が閉じる動きにより、まっすぐ方向へパワーを効率よく伝えられるようになります。
「スイングの時はラジオ体操のように右腕を前に、左腕を後ろに振り出す」これが出来れば身体が開いてしまうミスを減らすことが出来ますよ!
非利き手を離すのが早いと、手打ちになってしまう
片手バックハンドストロークは右手1本で打ちますが、右手だけでテイクバックからフィニッシュまで振ることは不安定につながります。
もしかしたら右腕の腕力がものすごい強い人はあまり気にならないかもしれませんが、通常逆手で打つことになる片手バックハンドストロークはただでさえ力が伝わりづらいので、右手だけだと不安定になりやすいと言えます。
またテイクバック時に右手だけでラケットを引こうとすると、身体の向きがあまりターンできなくなります。ボディーターンが少ないと手打ちになってしまい不安定感が増大することになります。
解決法→テイクバックは非利き手で!肩の入りを意識しよう!
片手バックハンドストロークのレディポジション(構え)では右手はグリップ、左手はスロート(ラケットの真ん中の三角部分)を持つことが一般的です。
テイクバックで十分なボディーターンを実現させるためには、右手でラケットを引くのではなく、左手でスロートを持ちながらテイクバックをしましょう。
左手で引くと、右肩がグッと左方向に引っ張られることが分かるかと思います。そのまま左手を後ろに持ってくると右肩がしっかりと入った状態でテイクバックが出来ます。これがしっかりとボディーターン出来た状態です。
また、左手を握ったまま(両手で)テイクバックすることにより、テイクバック完了時の面の不安定感が無くなります。それが出来てから、はじめて左手をリリースして(離して)スイングに入っていく。こうすることでインパクト時の面も安定することが出来ます。
「テイクバックは左手を使って、ボディーターンをしっかりと行う」片手という言葉にとらわれ過ぎず、左手を上手く活用することが安定への近道です!
まとめ
バックハンドストローク(片手)が安定するための解決法
・正しい打点から逆算してテイクバックやスタンスの準備をしよう!
・ラジオ体操の動きで、右肩の開きを抑えて、肩甲骨が閉じる動きを感じよう!
・左手でテイクバックをすることによって、右肩の入りと面の安定性を高めよう!
難易度が高いと言われがちな片手バックハンドストロークですが、力の入り方を覚えてコツをつかめば安定感を得ることが出来ます!フェデラーのような美しい片手バックハンドを目指しましょう!
以上、参考になれば幸いです!
両手バックハンドストロークのコントロール改善は、「バックハンドストローク(両手)が狙い通りに飛ばない方への解決法(初級編)」で詳しく解説しています。
他のショットにお悩みの方は、「テニスショットお悩み解決」リストからご覧ください!
ゲーム戦術でお悩みの方は、「ゲーム戦術お悩み解決」リストからご覧ください!
テニスギア、アクセサリの解説とお勧めは「テニスギアお悩み解決」リストからご覧ください!
上達の為の考え方は、「テニス脳~上達の為の考え方~」リストからご覧ください!
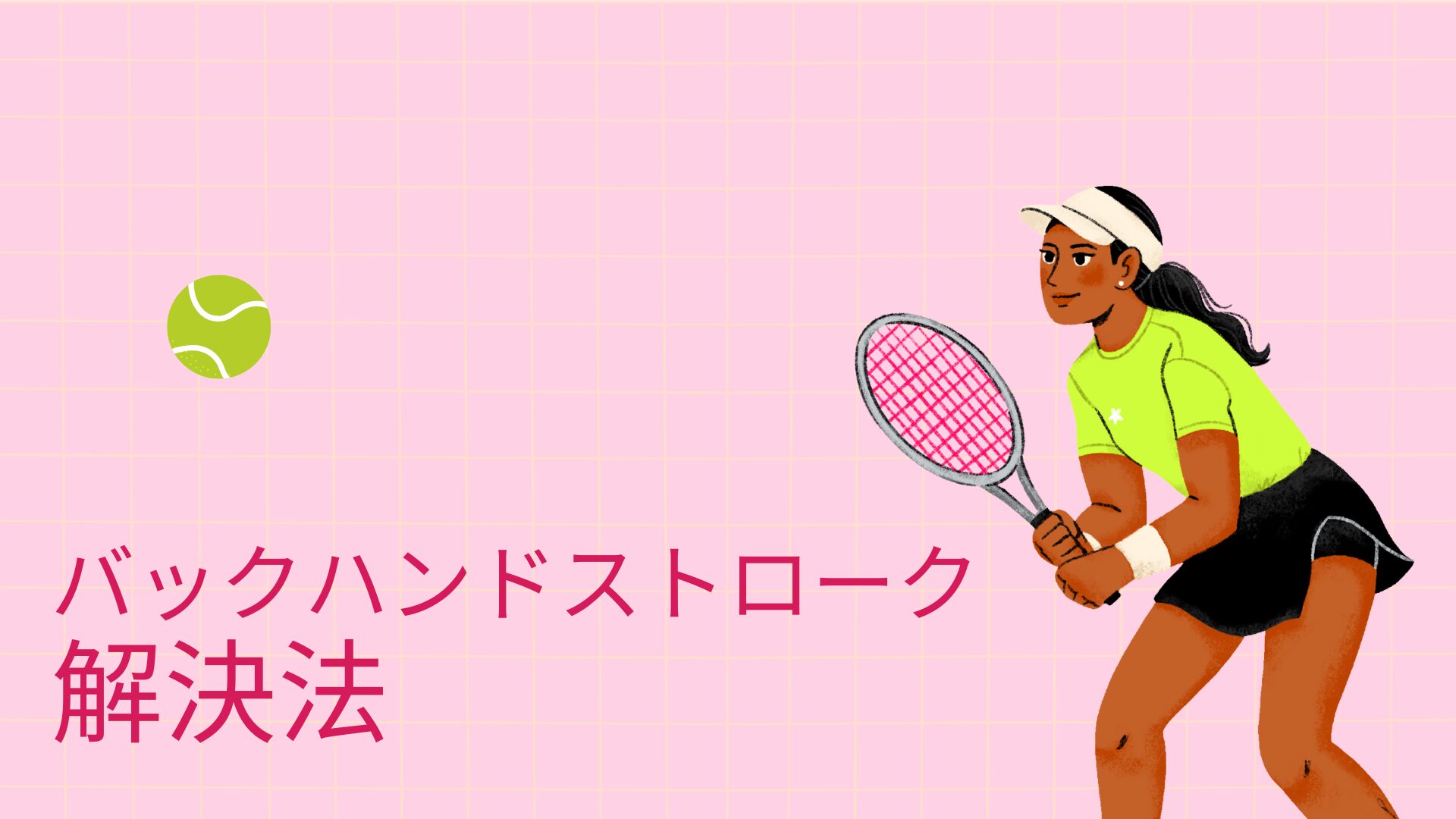


コメント